■日時:平成30年3月13日(火) 11:30~13:00
■場所:国立情報学研究所19階 会議室1(1901室)
東京都千代田区一ツ橋2-1-2
議題:
1)開会の辞
2)議長選出
3)議案
第1号議案 平成29年度活動・事業報告
第2号議案 平成29年度会計収支報告、監事報告
第3号議案 平成30年度活動・事業計画
第4号議案 新理事候補者にともなう役員選挙
2017年12月19日(火)にGRACEワークショップ、12月20(水)にGRACEシンポジウムが開催されました。NPO法人トップエスイー教育センターはこの2つのイベントを後援致しました。
GRACEシンポジウム詳細
GRACE Symposium 2017 – Next Ten Years of Software Engineering
2017年6月29日(木)に実施された「第19回 OSSユーザーのための勉強会」では、AI/Deep Learning 分野での活用が注目されているプログラム言語の「 Python 」を題材に、その概要から詳細な解説に至るまで、ご紹介していただきました。

今回の勉強会では、AI/Deep Learning 分野での活用が注目されているプログラム言語の「 Python 」をテーマに、その概要・特長・最新動向や、AI/Deep Learning 分野における活用について、株式会社ビープラウドの鈴木さん、株式会社CMSコミュニケーションズの寺田さんにご紹介していただきました。
また勉強会のあとの懇親会でも、参加者の有志の方から興味深く、熱いライトニング・トークが行われ、会場は参加者の熱気に溢れ、参加者同士の意見交換など活発な交流が行われました。
以下に発表資料を公開しております。
http://www.scsk.jp/product/oss/report2.html
・開催日時:2017年6月29日(木) 18:30~ (20:15終了予定、開場 18:00)
・プログラム
1.「 Pythonの特長と最新動向 」(仮題)
株式会社ビープラウド Python Climber、一般社団法人PyCon JP 理事 鈴木たかのり
2.「 AI/Deep Learning 分野におけるPythonの活用 」(仮題)
株式会社CMSコミュニケーションズ 代表取締役、一般社団法人PyCon JP 代表理事
寺田 学
3. Q&A、ディスカッション
~ 終了後 懇親会(参加無料)~
4. 参加者によるライトニング・トーク(LT):懇親会で実施
※ 予告なくプログラム内容が変更される場合がございます。最新の情報は以下
のページでご確認ください。
http://eventregist.com/e/ossx2017-06
※ 記載されている製品/サービス名称、社名、ロゴマークなどは該当する各社
の商標または登録商標です。
・問い合わせ、登録フォーム
以下のページからご登録ください。
http://eventregist.com/e/ossx2017-06
2017年2月23日(木)に実施された「第17回 OSSユーザーのための勉強会」では、データセンター自動化ツール(構成管理ツール)の「 Ansible とChef 」を題材に、その概要から詳細な解説に至るまで、ご紹介していただきました。
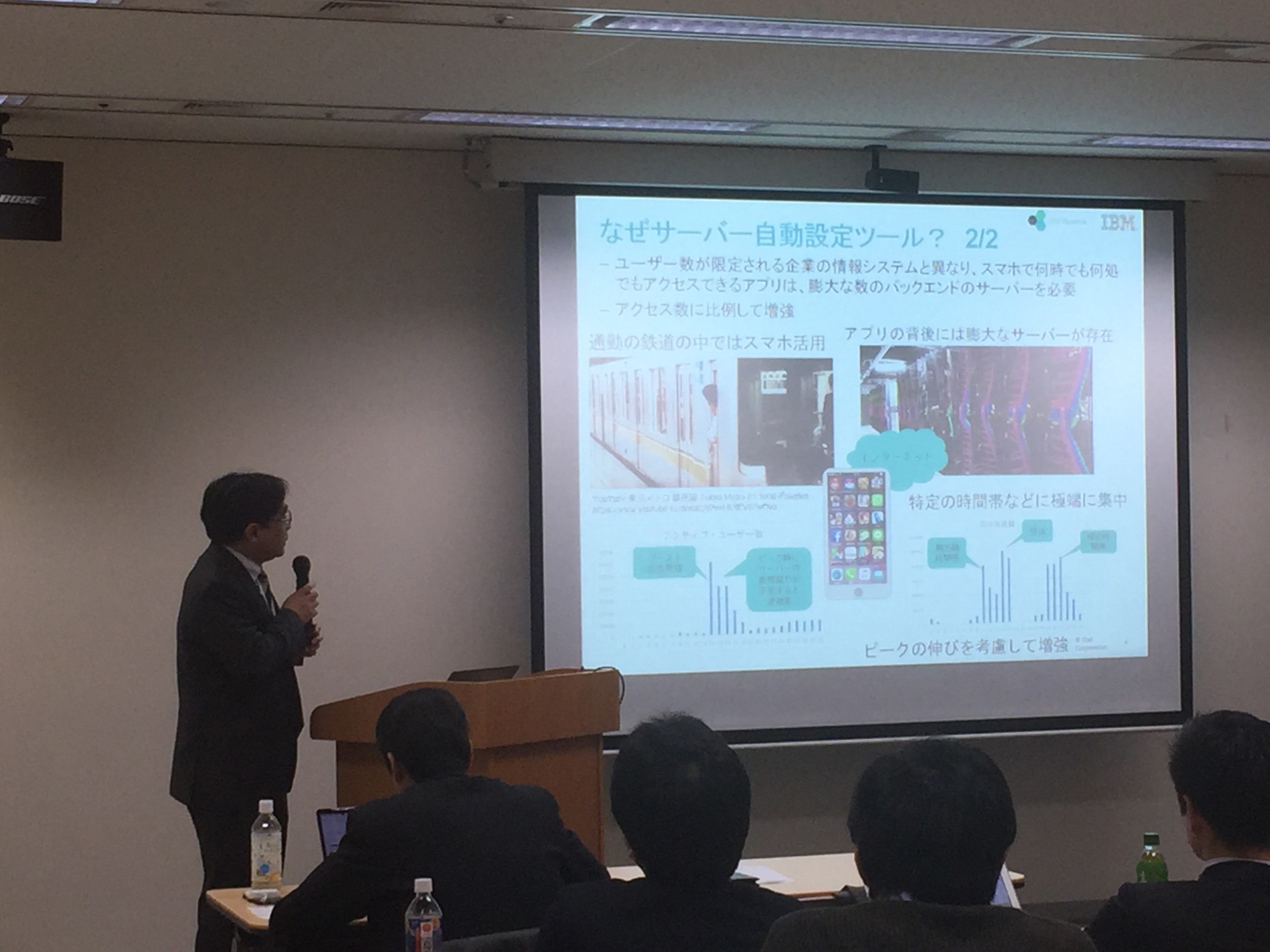
今回の勉強会では、データセンター自動化ツール(構成管理ツール)の「 Ansible とChef 」をテーマに、その特長・アーキテクチャ・最新動向・今後の展望について、日本IBMの高良さん、レッドハットの安斎さんにご紹介していただきました。
また勉強会のあとの懇親会でも、参加者の有志の方から興味深く、熱いライトニング・トークが行われ、会場は参加者の熱気に溢れ、参加者同士の意見交換など活発な交流が行われました。
以下に発表資料を公開しております。
http://www.scsk.jp/product/oss/report2.html
・開催日時:2017年2月23日(木) 18:30~ (20:15終了予定、開場 18:00)
・プログラム
1.「 Chef の概要と特長」(仮題)
日本IBM㈱ エキスパート・テクノロジー・アーキテクト 高良 真穂
2.「 Ansible の特長と最新動向 」(仮題)
レッドハット㈱ シニア・ソリューションアーキテクト 安斎 宗一郎
3. Q&A、ディスカッション
~ 終了後 懇親会(参加無料)~
4. 参加者によるライトニング・トーク(LT):懇親会で実施
※ 予告なくプログラム内容が変更される場合がございます。最新の情報は以下
のページでご確認ください。
http://eventregist.com/e/ossx2017-2
※ 記載されている製品/サービス名称、社名、ロゴマークなどは該当する各社
の商標または登録商標です。
・問い合わせ、登録フォーム
以下のページからご登録ください。
http://eventregist.com/e/ossx2017-2
1. Introduction to behaviour models
2. Modelling concurrency.
3. Brief intro to linear temporal logics
4. Controller synthesis in MTSA
5. Enactment of controllers
MTSA: http://mtsa.dc.uba.ar
本講義は英語にて行われます.
講師
Nicolas D’Ippolito助教, ブエノスアイレス大学
http://lafhis.dc.uba.ar/en/~dippolito
講師:坂本一憲(国立情報学研究所)
事前に指定口座に受講料をお振り込み下さい.請求書が必要な方は別途NPO法人トップエスイー教育センター事務局(inquiry@topse.or.jp)までお問い合わせ下さい.
2016年11月22日(火)に実施された「第16回 OSSユーザーのための勉強会」では、脆弱性スキャナーの「 Vuls 」を題材に、その概要から詳細な解説に至るまで、講演していただきました。

今回の勉強会では、脆弱性スキャナーの「 Vuls 」をテーマに、その概要から詳細な解説に至るまで、フューチャーアーキテクトの林さんと神戸さんにご紹介していただきました。
また勉強会のあとの懇親会でも、参加者の有志の方から興味深いライトニング・トークが行われ、会場は参加者の熱気に溢れ、参加者同士の意見交換など活発な交流が行われました。
以下に発表資料を公開しております。
http://www.scsk.jp/product/oss/report2.html
今回は脆弱性スキャンツール「 Vuls 」を題材に、その特長・アーキテクチャ・最新動向・今後の展望についてご紹介いたします。
また今回も、ユーザーからのご意見・ご要望を表明する場として、参加者によるライトニング・トーク(LT)の時間を設けています。
最新のOSS動向に触れるチャンスとして、お気軽にご参加ください。セッション終了後にはささやかな懇親の場を用意しております。
・開催日時:2016年11月22日(火) 18:30~ (20:15終了予定、開場 18:00)
・プログラム
1.「セキュリティの現状とOSSの応用」
フューチャーアーキテクト㈱ スペシャリスト 林 優二郎
2.「脆弱性スキャナーVuls徹底入門」
フューチャーアーキテクト㈱ スペシャリスト 神戸 康多
3. Q&A、ディスカッション
~ 終了後 懇親会(参加無料)~
4. 参加者によるライトニング・トーク(LT):懇親会で実施
※ 予告なくプログラム内容が変更される場合がございます。最新の情報は以下のページでご確認ください。
http://eventregist.com/e/ossx2016-11
※ 記載されている製品/サービス名称、社名、ロゴマークなどは該当する各社の商標または登録商標です。
・問い合わせ、登録フォーム
以下のページからご登録ください。
http://eventregist.com/e/ossx2016-11
CafeOBJは、代数的にシステムの仕様を記述し、その上の性質を証明することができる先端的な形式仕様言語の一つです。本講義では、CafeOBJを使った代数仕様言語の記述方法とシステムの性質を対話的に証明する方法を実際に支援ツールを使いながら学ぶことができます。
講義は2日間にわたって行われ、自然数やリストを使ったCafeOBJによる代数仕様記述の記述方法から、具体的な相互排他プロトコルを使った対話的な証明まで、ツールを通して体験していただけます。CafeOBJの開発者の一人である二木特任教授から直接学ぶことができるまたとない機会となっております。
当日会場に用意されたシンクライアントにて演習を行うことができます。ご自身のPCで動かしてみたいという方は、以下のページからCafeOBJ 1.5.5をインストールしてご持参ください。
※本講義は、2015年10月23日に行われた内容に「仕様計算(Specification Calculus)による場合分けの自動化」の解説と演習が追加されています。
講師:北陸先端科学技術大学院大学 ソフトウェア検証研究センター 特任教授 二木厚吉
以下のページから最新の講義資料をダウンロードできます。http://www.jaist.ac.jp/~kokichi/lecture/1609NII/
※講義資料は英語が中心となりますが、講義は日本語で行います。
「CafeOBJ入門」
(1) 形式手法とCafeOBJ: http://ci.nii.ac.jp/naid/110006664762
(2) 構文と意味: http://ci.nii.ac.jp/naid/110006664763
(3) 等式推論と項書換システム: http://ci.nii.ac.jp/naid/110006840405
(4) 証明譜による検証法: http://ci.nii.ac.jp/naid/110006990888
(5) 認証プロトコルの検証: http://ci.nii.ac.jp/naid/130004549136
(6) 通信プロトコルの検証: http://ci.nii.ac.jp/naid/10025982447