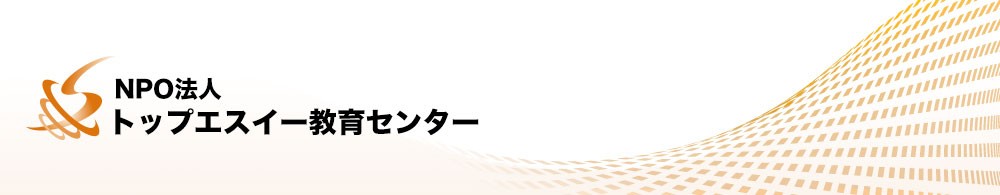2015年7月29日(水)に実施された「第10回 OSSユーザーのための勉強会」では、オープンソースのオンラインストレージ、ファイル共有ソフトである「 ownCloud 」を題材に、勉強会を開催いたしました。

勉強会概要
今回の勉強会では、OSSのオンラインストレージ、ファイル共有ソフトである「 ownCloud 」を題材に、その特長・アーキテクチャ・最新動向・今後の展望について、株式会社ビーグッド・テクノロジーの高橋さんより、認証ソフトのOpenAMと連携した活用事例のご紹介を株式会社オージス総研の千野さんよりご講演いただきました。
また勉強会のあとの懇親会では、飛び入り1名を含め4名の方から興味深いライトニング・トークが行われ、会場では参加者同士の交流、意見交換が活発に行われました。
以下に発表資料を公開しています。
http://www.scsk.jp/product/oss/report2.html
SCSK株式会社では、NPO法人トップエスイー教育センターの協賛の下、注目すべきオープンソースソフトウェア(OSS)を題材に、開発コミュニティとユーザーコミュニティ、そしてこれから学びたい人々の交流を図る勉強会シリーズ「OSSユーザーのための勉強会」を開催しております。
今回は、オープンソースのオンラインストレージ、ファイル共有ソフトである「ownCloud」を題材に、その特長・アーキテクチャ・最新動向・今後の展望および、その利用事例についてご紹介いたします。
また今回も、ユーザーからのご意見・ご要望を表明する場として、参加者によるライトニング・トーク(LT)の時間を設けています。最新のOSS動向に触れるチャンスとして、お気軽にご参加ください。セッション終了後にはささやかな懇親の場を用意しております。
プログラム:
1.「ownCloud の特長と最新動向」(仮題)
株式会社ビーグッド・テクノロジー ITサービス統括部 システム開発グループ
リーダー 高橋 裕樹
2.「活用事例紹介:OpenAM(ThemiStruct-WAN)と連携し、SSOを実現」(仮題)
株式会社オージス総研 サービス事業本部 テミストラクトソリューション部
プロフェッショナルサービス第一チーム 技術チーム 千野 修平
3. Q&A、ディスカッション
~ 終了後 懇親会(参加無料)~
4. 参加者によるライトニング・トーク(LT):懇親会で実施
※ 予告なくプログラム内容が変更される場合がございます。最新の情報は以下のページでご確認ください。
http://www.scsk.jp/event/2015/20150729_3.html
※ 記載されている製品/サービス名称、社名、ロゴマークなどは該当する各社
の商標または登録商標です。
※定員に達し次第,申し込みを締め切らせていただきます。
URL:http://www.scsk.jp/event/2015/20150729_3.html
株式会社ビーグッド・テクノロジー、株式会社オージス総研